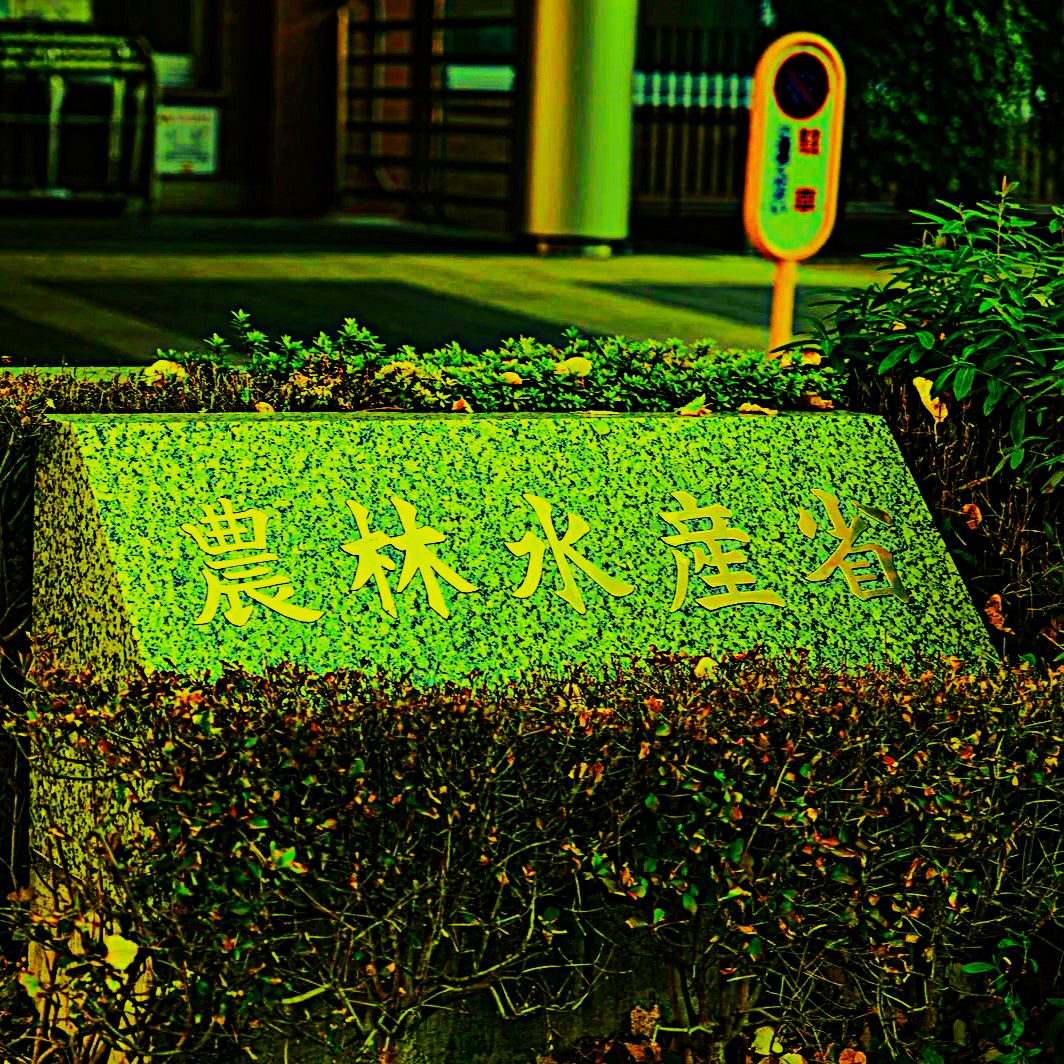江藤拓農相は4月15日の閣議後定例会見で、放出しても迅速・公平には行き渡らない政府備蓄米をめぐって、3回目の売渡入札では何らかの工夫を凝らすとの考え方を示した。集荷業者ではなく卸売業者に直接売り渡すアイデアに対しては、全国団体から「オーダー処理などで不慣れだし、集荷も難しい。多数が入札に参加すると、価格が逆に高騰してしまう恐れがあり、適切ではないとのご意見を頂戴した」と、集荷団体と同様、だらしない体質が浮き彫りになる情況を明らかにしている。
一問一答(4月15日、閣議後定例会見から抜粋)
記者 明日から赤沢大臣が渡米してトランプ政権との交渉が始まりますけれども、農水省としてどのような主張、要望をされている状況でしょうか。また、アメリカ側からはたびたび農産物への言及がありますが、渡米や対策本部のメンバーに、農水省から人員を入れることは検討されている状況でしょうか。
大臣 報道等では行かれるということになっていますが、政府としてはまだ正式決定しておりませんので、正式決定していない以上、このことについてコメントすることはできません。ご理解いただきたいと思います。そして、農林水産省からの同行についてのご質問ですが、これについても赤沢大臣自体が決まっていないということですから、今、この時点では、お答えできないということでお許しいただきたいと思います。
記者 昨日の意見交換会について伺います。昨日、意見交換会で卸(売業者)や小売業者の方々と意見交換されたと思うのですが、もともとは石破首相からの、米の高止まり解消への取組を要請するという指示のもとで行われた意見交換会だと思いますが、昨日大臣から具体的にどのような要請をされたのかお聞かせください。もう1点、意見交換会で卸や小売業者の方から出た意見の中で、今後、備蓄米の運用ルールの改善を検討されるような点がありましたら、お聞かせください。
大臣 まず、(備蓄米放出を)1回、2回と行い、卸の方も小売の方々も、できるだけ店頭に早く並べるように御努力をいただいておりますから、そのことについては、まず率直にお礼を申し上げさせていただきました。その上で、やはり国民、国の財産である備蓄米を放出して、それを扱うということは、通常の商取引とは若干違う。しかし、国がなぜこのような決断に至ったのかということを、各流通段階の方々もぜひご理解いただきたい。政策実現のために協力してくださいということまでは申しませんが、あくまでも皆様方は商取引をされているわけですから、義務を課すことはできませんが、国の意図、私の心情についてはご理解いただきたい、と申し上げました。
そして昨日は、皆さんご存じのように、大手の卸の方、中小の卸の方、大手のスーパーの方、地方を中心とする小規模なスーパーの方、それから町のお米屋さんの代表の方、幅広い関係者の方々にご出席いただき、全員の方からそれぞれコメントをいただきました。約1時間半議論をさせていただきました。非常に内容のある会で、私自身もなるほどと気づきのある点が多数ありました。内容としては、日頃集荷業者と取引がない卸もおり、急に取引といっても、窓口がいないので難しいということがあるので、そこはちょっと工夫して欲しいと。バランスをとって、日頃つき合いのない卸の方々にも米が行き渡るように、ぜひ3回目については、集荷業者の方々にも指導するなり、工夫をして欲しいというようなご意見。それから、備蓄米を直接卸に売るというスキームについては、オーダー処理などで大変不慣れであるし、集荷も難しい。そして、卸は600社いますから、その方々全部にはならないでしょうけど、多数の方々が入札に参加されると、価格は逆に高騰してしまうおそれがあり、適切ではないという卸の方からのご意見。小売の方々からは、できるだけ幅広い小売が、備蓄米を扱えるように、例えば、大手のスーパーの方が来られて、うちではこれだけの数、今、備蓄米を確保できていますという数字も示されました。しかし、中小の地方の方々は、私たちのところには全くないですというご不満の声もありました。
備蓄倉庫の偏在、距離の問題、輸送の問題、様々な問題があり、私は記者会見で、4月10日ぐらいには店頭に並ぶということを申し上げたのですが、特に中小の方々からは、早くて5月末、5月になってしまうかもしれないという率直なお声もいただきました。備蓄米を放出したことが、規模の大きいところだけではなく、町のお米屋さんも含めて、均等に行き渡るような工夫を、我々としてもしなければいけないと思います。
そして、生産と流通の情報をもっとしっかり把握して、小売の方々から、情報発信にはさらに力を入れて欲しいというご意見がありました。言いたいことはまだまだいっぱいあるんだという方が大分おられました。ぜひ折に触れてこのような会をしたいと。今日このような会をやってくれて非常によかったと評価をいただいた。物事は進むにつれて、やればやるほど、もっとこういう工夫もあるよね、こうした方がいいよねと、ブラッシュアップしていく必要があります。必要に応じて、あれだけのメンバーの方に集まってもらうのは大変ですけれども、またお声掛けして、しっかりとした流通・小売の方々のご意見も聞きながら、これから備蓄米の放出を続けて欲しいと。特に卸の方からは、3回目以降も安定的に続けていただくことが、端境期に向けた安定に繋がるので、ぜひ続けて欲しいというご意見をいただいたところです。
記者 1点確認ですけれども、集荷業者から卸への販売について改善を求める声があったということで、3回目の入札からと今おっしゃいましたけど、3回目の入札にあたって通達を出すとか、そういう具体的な対応は考えられてますでしょうか。
大臣 1回目、2回目は、同じメンバーで入札をしました。3回目については、入札資格審査について、もう1回やろうと思っています。どのような数になるかはまだ全く見通せませんが、入札資格者の数が増えることによって枝葉は増えるわけです。落札された集荷業者の数が増えれば、隅々まで行き渡らせるのには一定の効果があるのではないかと。また、卸の段階でも、具体的に今日は申し上げませんが、こうして欲しいという具体的なお話は何点かいただきました。なるほどという気づきもありました。これは省内で検討の必要があります。これまでの商取引の慣習に関わることですので、慎重に検討した上で、また卸の方々とも話をしたいと思っています。やはり町の小さなお米屋さんのご意見としては、入ってくるというお話は、我々がお集まりいただきたいとお声がけをした段階は、金曜日(4月11日)です。月曜日(4月14日)の段階でも、できる限り各種団体のメンバーの方々の意見聴取には時間を割いてくれたようです。その中でもやはり小売、町のお米屋さんなんかでは、入ってきていないし、入ってくる見込みもないという率直な声もいただいたので、そこは何とか改善しなければならない。あとは学校であったり病院であったり、そういったところについては、診療報酬と見合いもあるので、なかなか厳しい現状もあるんですよと、様々な話をいただきました。
記者 アメリカの関税の交渉の関係でお聞きします。これまでアメリカ側が農産品の関税の引き下げや、農産品の市場アクセスの改善を今後求めてきた場合、大臣として今後どのように対応できるのか。そもそも検討していく可能性や考えについて、特に米に関して発言が多く見受けられますが、この点に関してどのように考えているか、改めてお聞かせください。
大臣 報道ベースでは色々おっしゃっていることは聞いておりますが、オフィシャルに政府間で「このようなものを、こうして欲しい」というオーダーが来たわけではありません。テレビを見て、誰々さんがああ言っているからといって日本の農水大臣として反応することはしません。これから正式に決定されれば赤沢氏が行くわけですから、赤沢大臣がしっかり相手の出方、何を求めているのか、具体的に何なのか、持って帰ってくるかもしれません。持って帰ってこないかもしれません。漠としたままかもしれません。
それを聞いた上で、また考えることはあると思いますが、今のところ米について具体的にどうしようとか、こうしようとかいう考えはありません。我々はガットのウルグアイ・ラウンド交渉のもとで、(㎏)341円という従量税をしっかり国際約束としてやっております。これは誠実な対応で、WTO上も何の問題もありませんから、そのことは申し上げておきたいと思います。
記者 先週は、4月10日くらいに備蓄米の1回目の放出分が店頭に並ぶと仰ってましたが、意見交換会の中でなかなか届いてないという声も聞いた上で、今でも4月10日ぐらいという見通しは変わらないのか、それとも、さらに遅くなるのか。
大臣 4月10日よりも早くに並んだところもあるのですが、全体のトレンドとして、あるところにはあるが、ないところにはないと。4月10日の店頭に並ぶというのは間違いではなかったです。特に中小の方々にお話を聞くと、我々のところにはようやく届いたぐらいの段階なので、4月末とか、5月に入ってしまうかもしれない。ましてや遠隔地は、輸送の手間もかかるので、私のこの間の発言よりも時間がかかるのではないかというご指摘もあったということです。